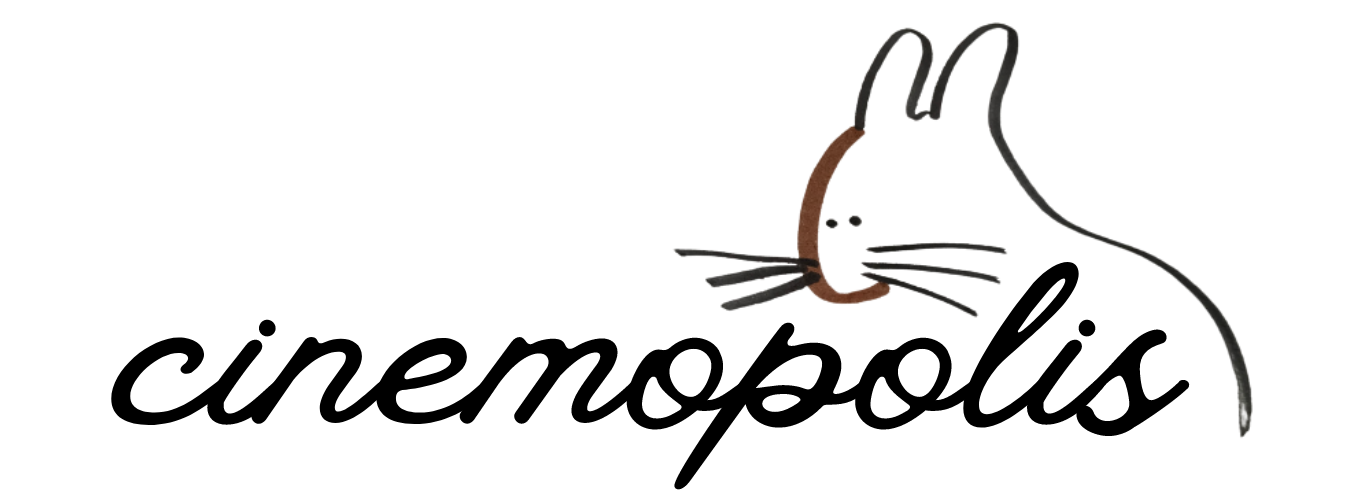「そして、私はスカーフを手に取って、自分を絞め殺すことを試みる。私が死ぬ前に、誰かが来てくれることを期待しながら。」ー『コンタクトホーフ』第一幕
その夜も私は、今見終えたばかりの『コンタクトホーフ』について話をしながら家路をたどっていた。ふと、第一幕の女の台詞を思い出して、あの台詞は何だったんだろうと言いながら、ぎくりと、全身に鳥肌が立つのを覚えた。ピナ・バウシュらしい独特のユーモアで、3日のあいだ、私を楽しませていた『コンタクトホーフ』が、その気づきと共に、違う作品に変容していくようだった。翌日、最後の公演を観たときには、それまで滑稽に見えて笑えていた場面も、実は真剣で痛切な感情に基づいていたように見えてきて、何度も息がつかえそうになった。次の動きを知るのが怖くなって、思わず目を覆ってしまうことさえあった。
「言語化されることをことごとく逃れる芸術」これまで、そう考えることで、私なりにピナ・バウシュの作品を捉えられるような気がしていた。彼女の作品は、ふいをつくように、よく知った感覚や手応えを思い起こさせる、それなのに、作品が何を表そうとしているのか、そう問われると、結局私は何も見ていなかったのではないかと心配になる程に、言葉が出てこないのだ。
ところがである『コンタクトホーフ』は、ひとつのテーマに基づいて、舞台の構成が行われているように思えた。それを頼りにすると、どの場面もある程度、私なりの説明が出来そうなのである。
そのテーマとは孤独、それも「極限の孤独」であった。ピナ・バウシュの作品で孤独のモチーフが見え隠れするのは、もちろんこの作品に限ったことではない。(それどころかおそらく彼女の全ての作品に共通するテーマとも言えるだろう。)しかしこの作品が他と違っているように見えるのは、人が孤立していく様子、その時の戸惑いや悲しみが、様々な人物によって、執拗、と言えるほどに何度も舞台上で表現される点である。その「孤独」の状態を、時に本人が、時に他人が、私たち観客に対して、必死に隠そうとしていることがこの舞台の痛々しさを、より一層強くしていることも見逃せない。
「すべてのものは、どこかですでに目にみえているのです」ピナ・バウシュはそう言うが、その言葉の通り、どの場面にも小さな事件が隠されているようである。
舞台上の人間は、私たちの世界の人間と同じで、皆、切に愛を求めている。しかし、そのすぐ隣りには、極限の孤独が横たわっている。皆の陽気さは「もっと他者に気にかけてもらいたい」「もっと私を見てほしい」という切迫した要求につながっている。舞台上の1人1人は、自身の存在を、少しでも多くの人から認めてもらうために、色んなことをする。手っ取り早く人の注目を集めるために、体を張って危ないことをする人もいれば、自らの性を、つまり女らしさを強調する場合もある。その危うさは、はっきりと舞台の影となって付き纏っている。こうして作品をみると、それまで抽象的なユーモアに覆われていた舞台のチャーミングな印象がすっと消え去って、急に緊迫を伴った作品に変化する。
わたしたちの日常の中で、劇場にいくのは、非日常で、特別な体験だ。『コンタクトホーフ』の舞台は、童心に返って、ダンサーにうっとりしたり、つい笑ってしまう場面がたくさんある。そんな本来の、劇場にいくという楽しみをしっかり満たしてくれる。それでいて、少し視点を変えてみると、そこには、人間の意識の本質的な孤独という、普遍的なテーマが、私の知っている他のどんな芸術よりも痛く、深く刻まれている。改めて、ピナ・バウシュの非凡な才能に気付かされるのである。